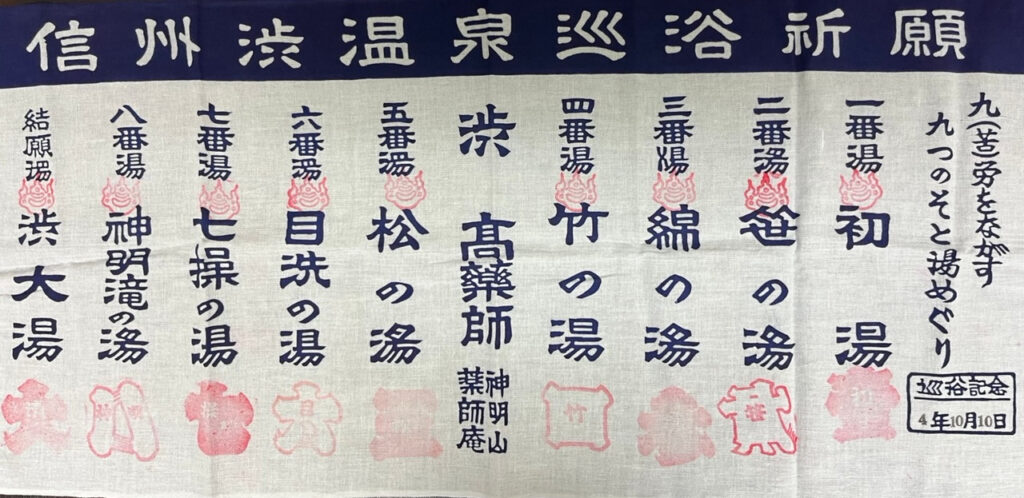2022.10.25 目の日に目洗い
10月10日は目の日です。
日本眼科医会では、毎年、目の啓発運動に取り組んでいます(院内ポスター多数貼付)。
院長も目新しいものを見つけに出かけてきました。
今回は、長野県・渋温泉に。
開湯1350年の古い歴史のある温泉です。
9つの外湯をめぐります。
元々外湯は、地域の共同浴場です。
組ごとの浴場があり、使用住民で維持・管理をしています。
宿泊客は『一泊住民』として、9つの浴場を使用できる鍵を借りられます。
扉の上側は組員用の鍵穴、下側は一泊住民用の鍵穴です。
巡浴祈願の手ぬぐいを手に出発。
レトロな温泉街に、9つの外湯が点在しています。
石畳の続く温泉街。
浴衣と下駄で歩くと、オバサン(院長)も、ロケ先のモデルのような錯覚に(自己陶酔)。
まずは初湯から。
1番目なので初湯。
胃腸に良く効く湯。
4~5人は入れるお風呂には、黄土色のお湯が。
どの湯も源泉からそのままの引湯なので、お湯ごとに違いがあります。
温度が高いので水で薄めるようにと表示。
やや熱いものの浸かれる許容範囲内。
1番湯達成、手ぬぐいにスタンプを押します。
気をよくして、2番湯へ。
湿疹に効く湯。
浸かろうと、足を突っ込んでみると…
若かったら『ギャーッ!』と悲鳴を上げたほど(オバサンなので、そこは冷静に)。
激熱!
水を入れようが、ちっとも適温にならず、足先だけ浸かって退散。
1番湯は誰かが薄めた後だったのでしょう。
(各浴場には、湯が熱いので火傷に注意の表示が)
3番湯は、綿の湯。
切創や皮膚病に効果あり。
白い湯花が綿を想像させるそう。
4番湯は竹の湯。
慢性痛風に効果あり。
5番湯は松の湯。
神経痛や病気の回復効果あり。
観光客は、浴衣を脱いで、ドボン(熱くなければ)と浸かっているだけなので、すぐわかります。
マイ桶に石鹼・シャンプー・リンスを持って入って来る人は、地元の人です。
5番湯の扉を開けたとき、出てきた母娘。
『娘と一緒に薄めといたから、無茶苦茶いい湯になってるよ。今、最高の湯だよ!』
『ありがとうございま~す』ひとり最高のお風呂で極楽極楽、感謝感謝。
6番湯は目洗いの湯。
これぞ、今回の旅の目的・目玉です。
今まで、眼病平癒の寺社を訪ねた院長ですが、温泉は初めて!
名前の通り、昔は、このお湯で目を洗って眼病を治したとのこと。
眼病に効果あり。
今まで訪問した寺社もそうですが、昔は、感染症(細菌やウイルスによる病気)が多く、抗生物質などないので、『洗い流す』ことが唯一出来た治療?だったのでしょう。
上水道もなく井戸水(もしくは川水・池水)の時代、水も清潔ではなかったはずです。
より、微生物の少ない水やお湯が出る場所が、眼病平癒の御利益があるとされたのでしょう。
現代では、清潔な水道水でも、目は洗わないほうがいい(眼科医の常識です)と、眼科医は言います。
涙液層を洗い流してしまうので、目を洗いたいときは人工涙液を勧めます。
もちろん、何か異物や薬液などが入った時は、まず大量の水で洗い流しましょう。
7番湯は七操の湯。
外傷性の障害や病気の回復期に効果あり。
8番湯は神明滝の湯。
婦人病に効果あり、子宝の湯とも。
9番湯は大湯。
万病に効き、9湯めぐりの総仕上げです。
結願を込めて入浴することがポイント。
目の日に、目新しい『目洗いの湯』で、目のことを考える眼科医です。
こちらもご覧ください
→目の霊山
→鎌倉好き